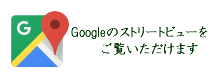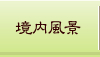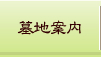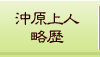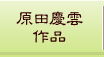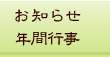綱脇妙龍上人
| 本秀寺30世 田中豊久 師匠(平成7年遷化) |
|
明治9(1876)-昭和45(1970)福岡県宗像市生まれ 日本で初めての民間のハンセン病療養所、『身延深敬園(じんきょうえん)』を つくったお上人で、60年以上もの長い年月にわたってハンセン病患者の救済に尽くした人です。 |
 |
◇明治9(1876)年1月24日、福岡県宗像(むなかた)郡池野村 (旧玄海町=宗像市)に ◇高等小学校卒業後の明治24(1891)年、和田屋という醤油醸造 業兼質古着商に奉公しましたが、
ひ弱な体質と過酷な労働により3ヶ月ほどで肺結核を患って帰郷。 ◇療養中に宗教心に目覚めます。明治25(1892)年1月檀那寺、法性寺の住職日良上人より ◇東京では、小石川若荷谷(みょうがだに)にある寄宿舎に入りました。 龍妙上人は ここで共同生活していた2人の友人と明治39(1906)年7月、身延山を訪れ 三門付近に群がるらい患者の様子を目の当たりにします。山形からきたという15〜16歳の 少年との出会いに深く心を動かされました。 祖廟(そびょう=日蓮聖人 のお墓)に参籍し、日蓮聖人の啓示を受け救らいの決意をします。 | |
|
●ハンセン病とは らい菌の感染によりおこる病気で、以前はらい病、ハンセン氏病とも呼ばれていました。 ハンセンは、明治6(1873)年にらい菌を発見したノルウェイの医師の名前です。 世界では年間約30万人の新規患者が報告されていますが、日本においては年に5名以下ということです。 国立ハンセン病療養所が13ケ所、私立が2ケ所あり、入所者数は平成18(2006)年12月現在3000名弱で、その多くが高齢者です。ほとんどの人がすでに治癒しているものの、社会復帰が困難なため支援を受けている実情があります。 治癒しているものの、社会復帰が困難なため支援を受けている実情があります。 |
◇綱脇龍妙上人は、御殿場のらい療養所「復生病院」(明治22年設立)を視察のため訪問します。 東京では内務省に通い、東京にきていた久遠寺法主の豊永日良上人に直談判して協力を得ます。同じ明治39(1906)年の10月12日、日本初の私立らい療養所『身延深 敬園(じんきょうえん)』を創立しました。 | |
◇当初は理解者が少なく多くの迫害や中傷が加えられ、国の社会福祉施策はまったくなく、 皇室のご仁慈以外のすべての経費は私財と托鉢、―厘講、篤志家の寄付で賄われまし た。一厘講というのは、毎日一厘ずつためたお金を寄付してもらうもので、―厘は今の 一円くらいです。寄付を求めて山梨県内だけでなく東京、 静岡、愛知、大阪、岡山、福井 などへも出かけました。大正9(1920)年財団法人の認可を得ます。昭和(1930)年には 九州に分院を開設しますが、こちらは昭和17(1942)年軍事保護院の要請により閉院し、 敷地を提供しました。 | |
◇妻の貞さんは大正10(1921)年に福井から身延へ移ってきました。深敬園の看護婦長と して留守を守り、昭和32(1957)年9月79歳で亡くなりました。龍妙上人は昭和45(1970)年12月に95歳で逝去され、娘の美智さんが深敬園の後継者になりました。 |
【晋役職歴・褒章など】 |
|
◆山梨県の社会福祉事業全般にも尽力し、昭和26(1951)年に設立された山梨県社会福祉協議会の初代会長を務めました。 |
|
◆昭和34(1959)年、日蓮宗大僧正に昇叙されました。 |
|
◆昭和43(1968)年、身延町名誉町民に推戴されました。 |
|
◆身延深敬園創立経営の功績により |
|
大正10(1921)年、宮内省より銀杯を下賜 |
|
昭和3(1928)年、内務大臣より銀杯を下賜 |
|
昭和5(1930)年、貞明皇后より銀製花瓶並びに金一封を下賜 |
|
昭和15(1940)年、勲六等瑞宝章を受章 山梨県知事、厚生大臣より表彰 |
|
昭和32(1957)年、藍綬褒章を下賜 |
|
昭和39(1964)年、勲四等旭日小綬章 |
|
◆社会事業に尽滓の功績により |
|
昭和26(1951)年、山梨県知事より県政功労者として表彰 | |
昭和28(1953)年、厚生大臣より表彰、朝日新聞社より保健文化賞 |
|
昭和43(1968)年、山梨県教育委員会より文化功労者として表彰 |
|
昭和43(1968)年、日本仏教伝道協会より、仏教伝道実践者として仏教伝道文化賞を贈与 |
|
◆昭和45(1970)年、正五位勲三等瑞宝章を追賜されました。 |
|